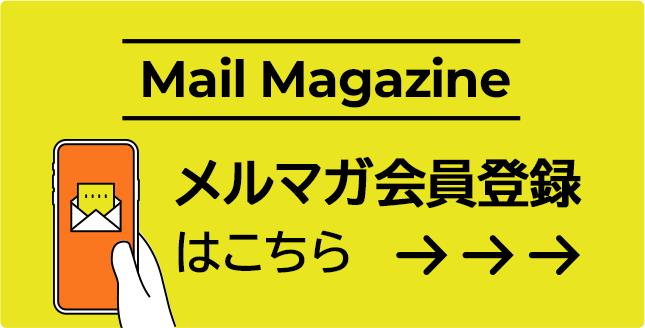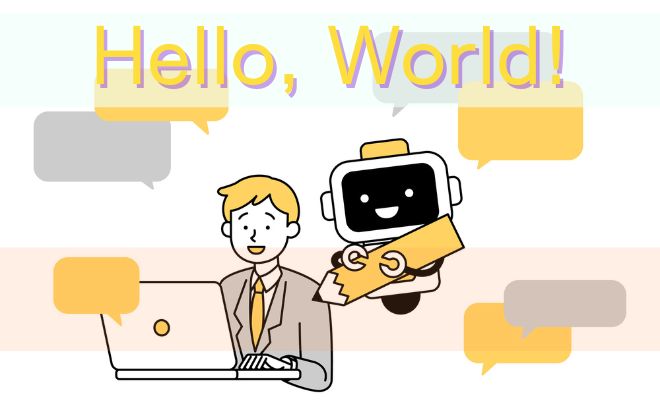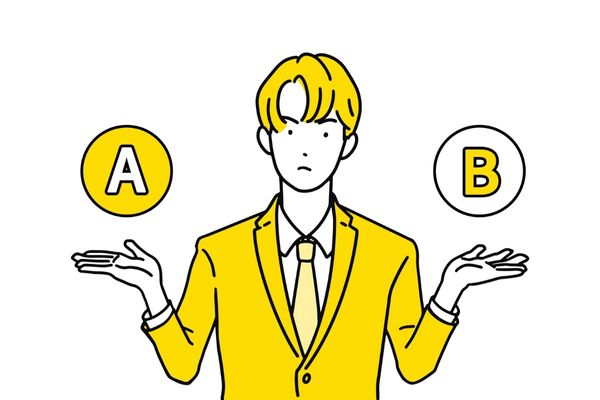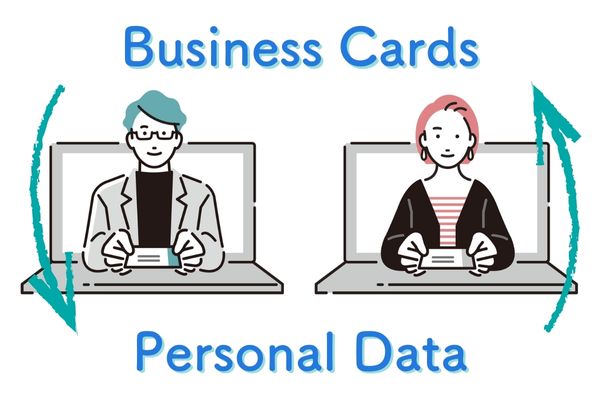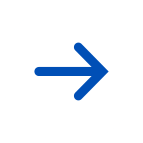コラム
2025/06/06
ついにスタート!「育児・介護休業法改正」…働き方はどう変わる?【社労士が解説】
公開日:2025年06月06日 更新日:2026年01月07日

※画像はイメージです/PIXTA
女性の社会進出が叫ばれて久しいものの、女性の3割はいまだに出産・育児を機に離職しているのが現状です(国立社会保障・人口問題研究所調査より)。こうしたなか、今年4月から段階的に施行される「改正育児・介護休業法」では、子育てと労働が両立できるよう多くの改正が行われました。今回の法改正のポイントについて、詳しくみていきましょう。社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。
■2025年4月から施行の「改正育児・介護休業法」
育児・介護休業法は、近年大きく変化しています。2022年10月に施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」をはじめ、職場における仕事と家庭の両立のための制度とその制度を利用しやすい環境づくりが注目されています。こうしたなか、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、柔軟な働き方を実現するための環境整備として、2024(令和6)年5月に育児・介護休業法が改正されました。この改正法は、2025(令和7)年4月1日から段階的に施行されます。
では、具体的にどのようなポイントで改正されたのでしょうか。共働き夫婦のA家、育児休業中のB家という2つのモデルケースをもとに解説します。
■「子の看護休暇」→「子の看護“等”休暇」に
「子の看護休暇」は、子どもの病気やケガ、予防接種を受けさせるために休暇をとることができる制度です。今回の見直しにより、対象の子の範囲が「小学校に就学するまでの子」から「小学校3年生修了まで」に延長されました。
さらに、看護だけでなく「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」でも休暇の取得も可能に。これにより、名称に「等」が追加され「子の看護等休暇」となりました。
・夫婦そろって卒園式に出られる!共働き夫婦Aさんのケース
A家には、今年度卒園を迎える子どもがいます。Aさんも夫もともに「卒園式は夫婦揃って出席したい」と考えていたものの、Aさんの勤務先の上司は、夫婦で子どもの行事に出席することに否定的。そのため、Aさんは子どもの晴れ姿を家族みんなで祝いたいと思っていてもなかなか休暇の申請を言い出せずにいました。
しかし、今回の法改正で卒園式のための休暇が法的に認められたことにより、堂々と「子の看護等休暇を取得したい」と申し出ることができるようになります。「卒園式も、入学式にも参加できるなんて! はりきって準備しなくっちゃ」と喜びのAさんです。
・感染症にともなう「学級閉鎖」でも取得可能
また、子どもが小学校に入学すると、集団生活のなかで感染症が流行し、学級閉鎖等になることがあるでしょう。仮に5日間学級閉鎖になると、曜日によっては丸5日間、連続して仕事を休まなければなりません。これまでは休むことが難しい、あるいは休むことを言い出しにくいと感じていた人も多いでしょうが、今後はこの場合も、看護等休暇制度を活用することができます※。
※子の看護等休暇の取得可能日数は1年間に5日、子が2人以上の場合は10日から変更ありません。
■「残業免除」の対象が3歳未満→小学校就学前に拡大
・子が小学校に入るまで残業ナシ!…育児休業中のBさんのケース
Bさんは、育児休業終了後に職場復帰する予定です。復帰後は子どもを保育園に預ける予定ですが、保育園のお迎えに間に合うよう、残業は避けたいと考えていました。残業免除については、これまで対象が「3歳未満の子」でしたが、改正後は「小学校就学前まで」と範囲が拡大されました。そのため、保育園に通園しているあいだは残業免除が可能となります。
「親には頼れないし、人手不足のなかで残業を断るのも忍びないと思っていたけれど、これで安心して子どもを保育園に預けられる!」
Bさんは大喜びです。
■短時間勤務制度の代替措置に「テレワーク」が追加
Bさんは育児休業のあと、いきなりフルタイムで働くことに不安がありました。そのため残業免除だけでなく、子どもが3歳になるまでの「短時間勤務制度」を使いたいと考えています。
短時間勤務制度とは、所定労働時間を原則6時間に短縮して働く制度です。業務によっては、短時間勤務制度を使うことが困難なこともありますが、その場合、会社は次の代替措置を講ずることになります。
2.フレックスタイム制度
3.始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤制度)
4.事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
5.テレワーク制度(2025年4月1日追加)
今回の制度改正で、5つ目の「テレワーク制度」が追加となりました。ただし、代替措置についてはBさんの会社の労使協定等の確認が必要です。
Bさんは今後の働き方について会社に意向を伝え、上司とともに法に基づいた柔軟な働き方を考えるそうです。
上記のほか、3歳未満の子を養育する労働者、または要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように、措置を講ずることが努力義務化されます。
■「介護離職」防止措置の義務化
介護については、いつ介護状態になるのか、いつまで状態が続くのかわかりません。介護離職することなく、両立支援制度の申し出が円滑にできるよう、研修、相談窓口や事例の収集・提供など、雇用環境が整備されています。
また、介護に直面した場合、個別に両立支援制度の周知・意向確認や、介護に直面する前の段階での情報提供が企業の義務となります。
・法改正は「働きたくても働けない」現役世代の“救い”となるか
今回紹介した以外にも、働く親の負担を軽減するために、今回の法改正では多くの制度で対象や条件が拡大されました。
育児・介護休業法は、育児および家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することが目的です。
「働きたくても働けない」現状から柔軟な働き方にスムーズに移行できるよう、段階的に施行されることとなっています。企業にとっても、制度を利用しやすい環境づくりは優秀な人材の確保につながるなどメリットが大きいといえます。
仕事と家庭(育児・介護)を両立できるよう、働く側・経営側双方が制度をよく理解することが重要です。
著者: 三藤 桂子 社会保険労務士法人エニシアFP 代表
(編集:幻冬舎ゴールドオンライン)
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
注目の
コラム記事
-

みがく / メキメキ
2026/02/13
【AIがしてくれること】 日常業務でのAI活用方法と注意点!
近年、働き方改革や人手不足、顧客ニーズの多様化を背景に、AIの導入が急速に進んでいます。営業現場でも...
-

みがく / メキメキ
2026/02/06
2種類のローン契約 「立替払契約」と「割賦販売契約」のちがい
シャープファイナンスのローン契約には「立替払契約」と「割賦販売契約」の2種類あります。どちらもお取引...
-

みがく / メキメキ
2026/01/30
個人情報とは?身近な名刺データの取扱いの注意点
現代社会において、情報の価値はますます高まっています。その中でも「個人情報」は、私たちの生活やビジネ...
[ 記事カテゴリ ]