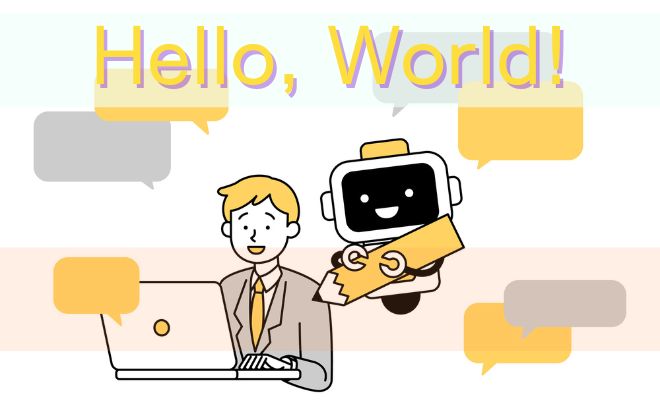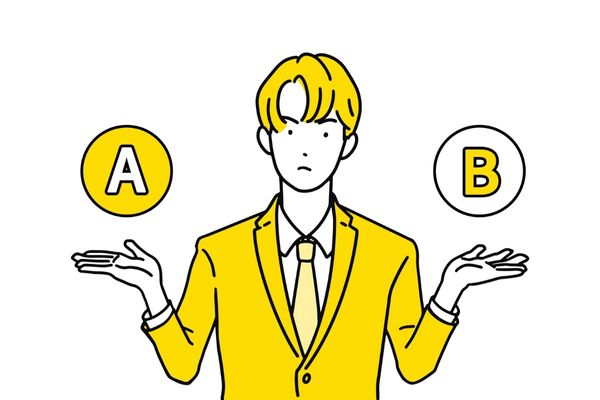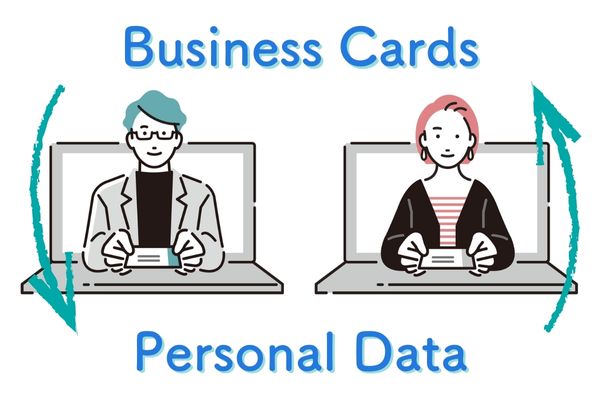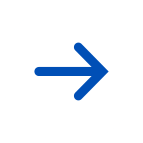コラム
2025/08/01
「火災保険」では ”損失がゼロにならない”? 「賃貸向け火災保険」の注意点【弁護士が解説】
公開日:2025年08月01日 更新日:2026年01月07日

※画像はイメージです/PIXTA
賃貸物件では、大家と入居者の双方が火災保険に加入することが一般的とされています。では、賃貸物件においてトラブルが生じた場合、賃貸人・賃借人のどちらのどの保険が利用できるのでしょうか、またそれはどのように判断すればよいのでしょうか。
賃貸物件でトラブルが起こる原因と「賃貸向け火災保険」の注意点について、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士が事例を交えて解説します。
■ “同じ建物”なのになぜ?大家・賃借人の双方が保険に入るワケ
賃貸借契約時に結ぶ契約条項の内容は、入居者に対して火災保険への加入を義務づける条項が盛り込まれているのが一般的です。一方で、大家もまた建物の損傷に備えて火災保険に加入していることがほとんどでしょう。同じ建物であるにもかかわらず、なぜ双方が火災保険に加入しているのでしょうか。それは、「火災保険」とひと口に言っても、契約内容によって補償範囲が大きく異なるためです。
まず、建物の所有者である大家は、建物の損傷自体に備えた火災保険+αに加入します。「火災保険」という名称ではありますが、地震や台風、飛来物によるケガへの対人保険、給湯器等の電気設備への特約を加えたものなどさまざまです。保険料との兼ね合いで補償範囲は調整するものの、火災のみならず建物およびその設備の損傷に備えた保険に加入するのが基本とされています。
他方、入居者は、建物の保護や建物内部の家財への補償を含めた内容の保険に入ることが多いでしょう。加えて、建物が区分マンションである場合、その物件独自の保険を利用するケースもあります。このように、賃貸人・賃借人はそれぞれ異なる内容の保険に加入しています。そのうえで建物内で損害が出ると、 “誰の、どの保険を利用するか”が問題となりトラブルに発展することがあります。
■ “誰の、どの保険”を利用するのか、できるのか?
たとえば明らかに加害者がいる場合、原則として加害者側の保険を使います。
しかし漏水など一部の問題では、加害者の責任によるものかどうか特定ができないケースも少なくありません。このような場合、被害者側の保険を使うことも検討します。現実的な話で、速やかに保険でリカバリーできれば当事者(被害者)のダメージが限定的になります。このような場合では保険金がおりた後、加害者側と被害者側の保険会社同士で「最終的にどちらが負担するのが妥当か」を調整することもあるようです。
区分マンションになるとさらに複雑です。トラブルの発生場所が「専有部分なのか、共用部分なのか」によって保険の適用先が変わるためです。専有部分であれば賃貸人または賃借人、共有部分であれば管理組合側の保険利用が対象になります。
また水道配管などは壁や床を壊して確認しなければわからないことも多く、判断が曖昧で弁護士や建築士が立ち会うことになるケースも珍しくありません。その上で原因の特定ができなければ最悪どの保険会社も保険金を支払わないというデッドロック状態に発展することも。被害者側が弁護士・建築士などを介入させて事態を能動的に解決していかざるを得ないということも起こり得ます。
とはいえ前向きに捉えれば、賃貸物件において損害が発生した場合、賃貸人(大家)か賃借人(入居者)、あるいはマンション管理組合いずれかが加入する保険によって賠償が受けられる可能性がある、ということは知っておくべきポイントでしょう。
■ 「火災保険」では ”損失がゼロにならない”? その理由
上記のように賃貸物件でトラブルが生じた場合、賃貸人または賃借人どちらかの保険のうち、使えるものを使って損害を補償していくというのが実務での感覚です。
ただ、保険を利用したからといって損失がゼロになるケースは多くありません。たとえば上階から水漏れがあった場合、入居者の家財にダメージが生じたとします。この家財に対する賠償額は、入居者の希望額と実際に支払われる保険料のあいだに、多くのケースで“ズレ”が生じるのです。
というのも、入居者の多くは「買ったときの金額で補償してほしい」と思いがちですが、損害賠償では、現在の金額(中古家財の市場価格や減価償却した金額)でしか補償ができません。法的には「中古品になっているものを新品価格で補償してもらう」のは現実的に難しいというのが実情です。
その差を埋めるために、自身が加入する火災保険は、買ったときの金額で補償される「新価補償」特約付きの保険に加入し損害に備えることも選択肢の一つです。
■まとめ:補償があっても「解決しない現実」がある
水漏れなど、賃貸物件におけるトラブルは、たとえ保険が使えても解決に至らない場合があります。補償の限界や、制度上の複雑さをあらかじめ理解しておくことが、リスク管理として重要なのです。
著者:山村 暢彦
弁護士法人 山村法律事務所 代表弁護士
(編集:幻冬舎ゴールドオンライン)
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
注目の
コラム記事
-

みがく / メキメキ
2026/02/13
【AIがしてくれること】 日常業務でのAI活用方法と注意点!
近年、働き方改革や人手不足、顧客ニーズの多様化を背景に、AIの導入が急速に進んでいます。営業現場でも...
-

みがく / メキメキ
2026/02/06
2種類のローン契約 「立替払契約」と「割賦販売契約」のちがい
シャープファイナンスのローン契約には「立替払契約」と「割賦販売契約」の2種類あります。どちらもお取引...
-

みがく / メキメキ
2026/01/30
個人情報とは?身近な名刺データの取扱いの注意点
現代社会において、情報の価値はますます高まっています。その中でも「個人情報」は、私たちの生活やビジネ...
[ 記事カテゴリ ]
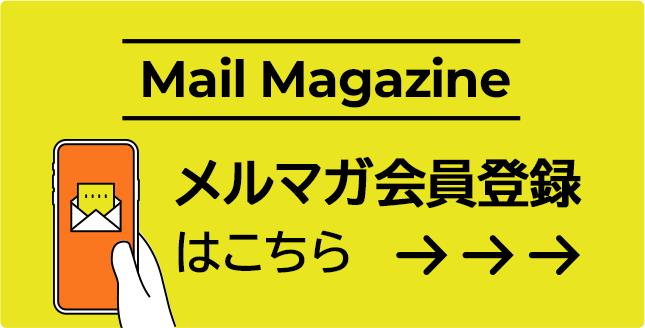
 2027年から変わる企業会計の常識 【新リース会計基準の全貌と対応を税理士が解説】
一覧へ
次の記事
2027年から変わる企業会計の常識 【新リース会計基準の全貌と対応を税理士が解説】
一覧へ
次の記事
 金利は上がり続ける?…マイホームを買う前に知っておきたい「住宅ローン」の賢い選び方【お金のプロが解説】
金利は上がり続ける?…マイホームを買う前に知っておきたい「住宅ローン」の賢い選び方【お金のプロが解説】