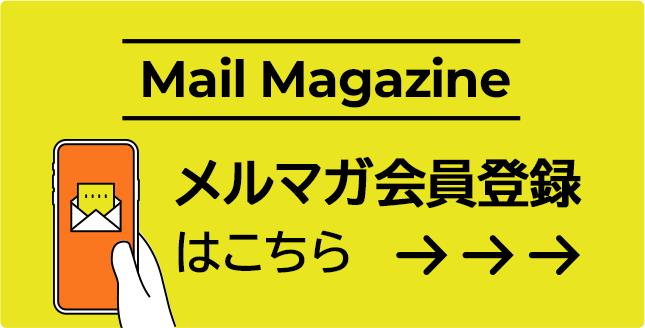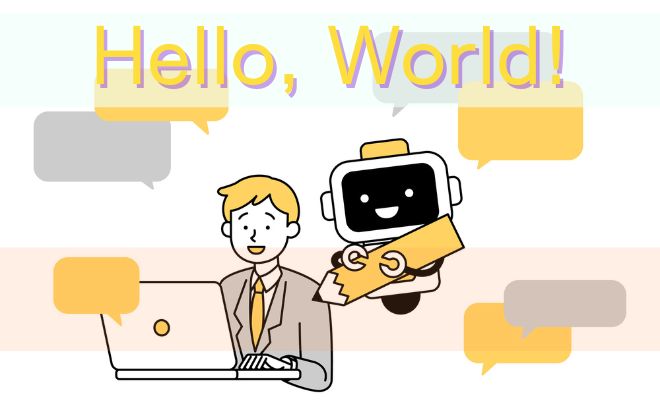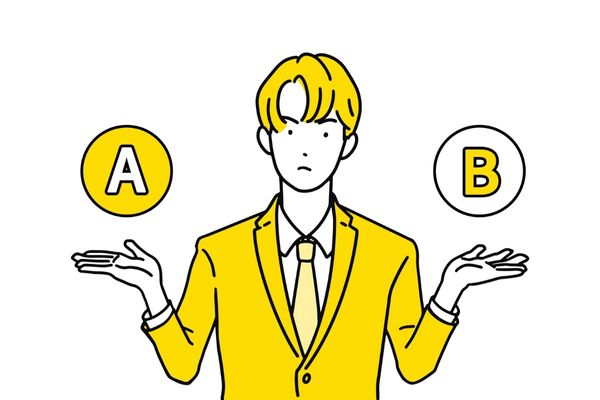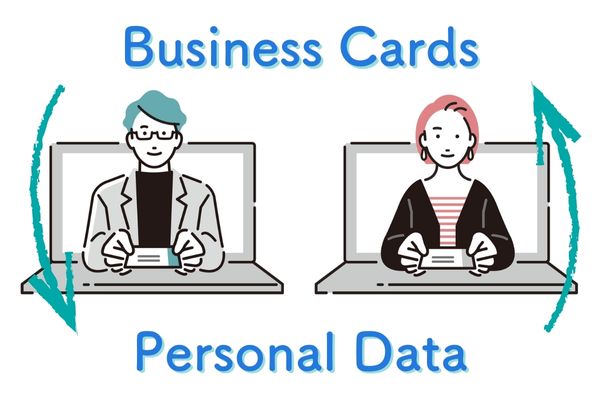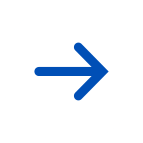コラム
2025/03/28
【キャリアコンサルタントと考える】2025年・新入社員の特徴と接し方
公開日:2025年03月28日 更新日:2025年06月26日

【問】氷が解けると「 」になる。の空欄を自由に埋めなさい。
上記は筆者が小学生の頃通っていた塾の算数講師に出された問いです。さあ、読者の皆さんはどんな回答をしましたか?
そして、今年の新入社員はどんな回答をすると思いますか?
新入社員の部門受入や研修の講師担当など接点が多い方も増える季節、今年の新入社員とどう接するかを一緒に考えてみましょう。
2025年新入社員の「働き方・キャリア」
2025年は75歳以上の後期高齢者が人口の1/5を占め、これまで以上に人材確保が難しくなって行くスタート年(2025年問題)とも言われています。そして、将来に向けて日本の働き方も大きな広がりが出始めています。
「週休3日制」「フルリモート/フレックス制」「シニア人材活用」「後継者不足」「賃上げ」「副業」「●万円の壁見直し」などキーワードは枚挙にいとまがありません。
当然ながら、昭和・平成初期の終身雇用・年功序列・労働組合という日本型雇用システムの三種の神器は、令和の新入社員には共感できないどころか、歴史教科書に載る時代のようなもの。受け入れにあたっては時代背景が全く違う未来人がやってきた!くらいのマインドセットをしておいた方が良いでしょう。
今年の新入社員は「冒険はしたくない安定志向」!?
今年の新入社員の傾向は「冒険したくない安定志向」と言われています。
ベンチャー・中小企業 < 大企業。給与やワークワイフバランスに敏感、地元志向(転勤拒絶)などの声に照らし合わせると、フムフムと納得できる傾向と言えます。
また、この世代は失敗を極端に嫌がり、一歩を踏み出すことに慎重です。例えば、新しいプロジェクトに取り組む際に、上司からの具体的な指示がないと動けないことが多く、自発的に行動することが難しいように見えます。
▼事例として…
(先輩)9:00 「午前中外出だから、このリスト先にテレアポ入れておいて」
→(新入社員)生成AIでセールストークを調べ、Yes-Noフローチャートでそれぞれの展開法を準備。固定電話に掛ける経験が無いため、脳内でシミュレーション…
→(先輩)12:30 「終わった?」→(新入社員)「まだ0件です!」
→(先輩)「3時間半も何してた???」
このようなすれ違い? の原因は個人の資質だけによるものではないようです。
思考要因のひとつは新型コロナ
今年入社になる四年制大学卒業生は、2020年入学=入学して1か月で緊急事態宣言が発出されたため、非対面コミュニケーションが主流となり、対外経験が少なく自己解決の機会・経験が乏しい。またオンラインコミュニケーションやSNSなどでリスク(炎上、衝突)を回避する習慣づけがあるため、自発性が低く見える傾向もあります。
その他、社会変化として「ハラスメント」「多様性」「メンタルヘルス」「SDGs/環境」「キャリア形成重視」などもあり、当然ながら密接に影響しているでしょう。
これらをまとめると、
■ 失敗したくない→指示待ちになる→ 自発性が育たない
■ キャリア志向が強くプライベート優先→ 個人主義志向
■ 競争がなくフラットな環境で育つ→ 環境の外で起きたことが理不尽に感じる→ 会社に馴染めない
といった成り行きが懸念される世代でもあります。
どうコミュニケーションを取れば良い?
新入社員と理解しあう近道は、1対Nではなく1対1でじっくりと向き合うこと。そう、巷でも話題に出るようになった「1 on 1」です。社会人の基礎(礼儀/言葉遣い/電話等)を0からなぞらせてやってみる。会社や組織では、どういう立ち居振る舞いが望ましいのかを時間を掛けて深めていく。
仕事とは何か、給与はどこから払われるのか、理想のキャリアを掴むには何を習得しなければならないのか、などを身近な例と対比して相互理解していくことが成長促進になると考えます。
 例えばCMでは転職サイトに登録したらすぐにスカウトが!と喧伝されますが、現実にはその準備/努力を積んだ人にしか相応しいスカウトは届きません。しかし、近年の若年層は全てがフラット、誰もがそのチャンスに恵まれると期待し、そうでないとガチャに外れたと他責になる傾向が強いよう感じています。
例えばCMでは転職サイトに登録したらすぐにスカウトが!と喧伝されますが、現実にはその準備/努力を積んだ人にしか相応しいスカウトは届きません。しかし、近年の若年層は全てがフラット、誰もがそのチャンスに恵まれると期待し、そうでないとガチャに外れたと他責になる傾向が強いよう感じています。
そのため、個々の事象に至る理由を論理的に諭していくようなコミュニケーションが求められるのでしょう。
ここまで読まれた方は『そこまでしないといけないの?』『まるで子育て!』という感覚を持たれた方もいるでしょう。確かに筆者も我が子よりも手が掛かると思いましたし、実務時間にここまで出来るか?と不安を感じます。
ただ冒頭に触れた2025年問題の通り、これから先は欲しくても人材確保が困難な時代です。入社してきてくれた金の卵を「きちんと育てていくこと」が非常に重要で、管理職であれば「育成ができる」という要件が評価指標に入る、もしくはこれまで以上に拡大すると思われます。
彼らが10年後も社内に居るかはわかりませんが、仕事の魅力ややりがいを感じて成長することで自社が成長する。そして仮に次へと飛び立ったとしても、その後輩たちが同じ成長曲線を描ければ、永続的な組織力維持に繋げることができます。
飛び立つ本人にもより大きなキャリアチャンスが拡がるのであれば、広く社会/国に人材輩出貢献を行った企業として、次の採用にメリットが出る時代になる。
そう思えば「やる」の一択と思えてきませんか?
研修やOJTで気を付けたいこと
では成長に向けてどうリードすれば良いのか? 各社が新入社員に求めているものには違いがありますが、各種調査では主体性/自律を求める声が高く、あるに越したことないというのが共通見解でしょう。まずはやってもらう仕事の目的を伝え、着実なステップアップのための声掛けから始めましょう。
子どもが補助輪を外して自転車に乗る時のように、時には転んでかすり傷を負うことも成長機会ですが、説明なくいきなり転ぶと「なぜ支えてくれなかった?」と離反してしまうリスクも有するため、意図を説明してチャレンジを評価しながら進めて行きましょう。
間違ってもやってはいけないことは感情的に怒ることです。「怒る」=主観で、意に沿わなかったことへのあなたの苛立ち表出に過ぎません。成長には「諭す」(リードに沿ったが起こった際)、「叱る」(確認不足等で自ら逸脱した際)を心掛けましょう。
それを続けていると、個々に成功パターンが生まれているハズです。出来るものは「型化」することで「結果→成長→自信」のサイクルが回り始めます。1年後、入社時とは違う顔で後輩を迎える準備にかかっているでしょう。
キーワードは「自分らしさ」と「振り返り」
新入社員は「働く事=自分事」ではありますが、ひとりで出来ることは多くありません。そのため、上司や先輩の指示通りに動くことが多く、自分に合わないやり方でも相談せずに無理をした働き方をしてしまう、そんな傾向もあります。結果、GW明けに出社せず退職代行から連絡がくるなど、ニュースで見たようなことも起こり得ます。研修やOJTでは目的・方法の確認とあわせて、これらを自分流にアレンジしてやりやすいのはどんな方法になる?と自分らしさと自主的な意見を引き出すことで、自律を促すことが出来るでしょう。
また、各社それぞれがPDCAやOODAでマネジメントサイクルを回していると思いますが、若年層には振り返りは価値が無いモノと捉える層が一定数存在します。「振り返る=自身の出来ていないモノを直視する」行為のため、回避思考が働くためです。ただ、同時に上手く出来たことの「成功型化」の機会も失っている点に気付けていないということなので、先輩の皆さんはぜひこの振り返りの重要性も意識して話しかけてみましょう。
ポイントは上記の通り「怒らないこと」と「成功を自信に変えて反復性を高める型化」です。
さて、冒頭の氷が解けると「 」になるの解、筆者は最初「水になる」が浮かびましたが、あまりにも平凡なので少し想像を働かせ、最終回答は「春が来る」としました。今振り返っても小学生ながら、なかなかの情緒的センス!
社会人になってからは人事畑が長かったため「春が来る→新入社員が入ってくる」と連想発想されるようになり、暖かな春のこのコラムに繋げてみました。
では、今年の新入社員はこの空欄にどんな言葉を紡ぐのか? 生成AIに、人事系各社がリリースしたアンケートデータ等を読み込ませて出た回答例が以下です。
「地球温暖化が進む」/「アイスコーヒーが完成する」/「冷凍庫が鳴り出す」
さあ、コミュニケーションを取る基準はイメージ出来ましたか?
とはいえ、近年のM-1審査員のように最初から90点ばかりつけていては「追いかけたい背中」としての先輩の魅力が欠けてしまいます。この上司/先輩に色々と教わりたい、成長したいと思われる自分らしい熱量で進めてみましょう。
ちなみに、10年以上前の酒席で上司にこの質問をした際の解は
「ママにおいしい水割りのおかわりを作ってもらう!」でした。
自分らしく、悠然と、大人な解(?)。
ここに辿り着く思考も地道な日々の実践で育まれると悟った春の思い出です。(笑)
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
注目の
コラム記事
-

みがく / メキメキ
2026/02/13
【AIがしてくれること】 日常業務でのAI活用方法と注意点!
近年、働き方改革や人手不足、顧客ニーズの多様化を背景に、AIの導入が急速に進んでいます。営業現場でも...
-

みがく / メキメキ
2026/02/06
2種類のローン契約 「立替払契約」と「割賦販売契約」のちがい
シャープファイナンスのローン契約には「立替払契約」と「割賦販売契約」の2種類あります。どちらもお取引...
-

みがく / メキメキ
2026/01/30
個人情報とは?身近な名刺データの取扱いの注意点
現代社会において、情報の価値はますます高まっています。その中でも「個人情報」は、私たちの生活やビジネ...
[ 記事カテゴリ ]