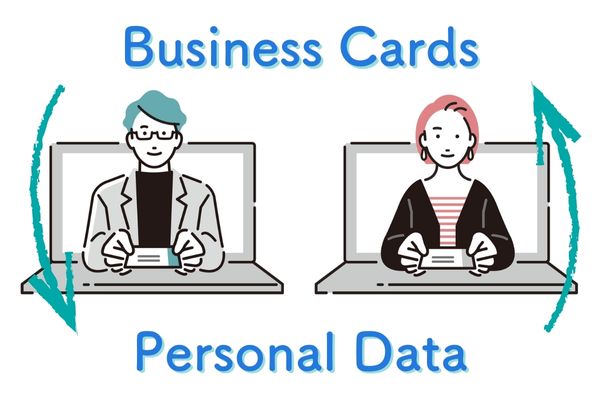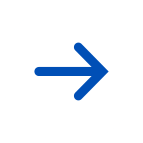コラム
2025/07/11
出世には興味ありません…クビにさえならなければいい?「静かな退職」を選ぶ若手社員の“懐事情”【お金のプロが解説】
公開日:2025年07月11日 更新日:2025年07月11日

※画像はイメージです/PIXTA
高度経済成長期~バブル期の日本では、プライベートを犠牲にしても仕事に全力を注ぐような働き方が良しとされた時代がありました。しかし近年、新型コロナの流行や経済の低迷などの社会的な背景から「静かな退職」という働き方を選ぶ若手社員が増えているそうです。「静かな退職」とはいったいなんなのか、またそのような働き方を選んだ場合に家計はどうなるのかなど、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。
■働き方が多様化するなか、「静かな退職」を選ぶ人が増えている
「静かな退職(Quiet Quitting)」という働き方をご存じでしょうか。これは、企業に所属しながら最低限の業務をこなし、あたかも退職したかのような精神的な余裕を持って働くことを指します。
いま、20代~30代前半の若手社員のあいだで、この「静かな退職」を選択する人が増えています。仕事とプライベートを明確に区分けし、仕事に対してやりがいなどを求めないのが「静かな退職」の特徴です。
「モーレツ社員」から「静かな退職」へ
かつて、日本の会社員は「モーレツ社員」や「企業戦士」と呼ばれ、プライベートを顧みずにがむしゃらに働くやり方が良しとされる時代がありました。また、当時は日本の雇用慣行として、1度入社したら定年まで同じ会社で働くという「終身雇用」が当たり前の時代でもありました。
時は流れ、「働き方改革」や「ワークライフバランス」が叫ばれるようになると、働き方も多様化し、1つの会社でずっと働き続けたいという人は減少傾向にあります。
厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」によると、今後「転職したいと思っている」割合は31.2%と特に20代前半の若者を中心に多く、若い世代は転職にあまり抵抗がないことがうかがえます。
転職を検討する理由としては、「賃金の条件がよい会社にかわりたい」が59.9%、次いで「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」が50.0%となっています。それ以外には、自分に合った仕事ができる会社や、自分の技術・能力が活かせる会社で働きたいと考えているようです(複数回答)。
以上から、若い世代が仕事を選ぶ基準は賃金だけでなく、労働時間や休日、休暇等、プライベートも重視していることがわかります。
また、厚生労働省の同調査では、若年労働者の職業生活の満足度D.I.※を雇用形態別に見た場合、若年正社員では「雇用の安定性」が66.4ポイントと最も高く、次いで「職場の人間関係、コミュニケーション」が57.3ポイント、「仕事の内容・やりがい」が55.2ポイントとなっています。
※「満足度D.I.」……現在の職場での満足度について、「満足」または「やや満足」と回答した労働者の割合から「不満」または「やや不満」と回答した労働者の割合を差し引いた値をいう。
若手社員にとって、仕事において満足度が高いのは「やりがい」よりも「安定性」や「居心地の良さ」にあるようです。
では、こうした働き方を選んだ場合、家計にはどのような影響があるのでしょうか。
■出世を望まなければ、給料も上がらない
ここでは、30歳のAさんを例にみていきます。Aさんの基本情報は下記のとおりです。
・Aさん(30歳)
・独身
・年収360万円(月々の手取り額:約25万円)
・プライベートの充実を重視し、出世は望まない働き方を希望している
厚生労働省「新規学校卒業者の初任給情報【確定版】(過去10年)」によると、大卒の初任給は2024(令和6)年3月卒で男性が23万8,000円、女性は23万5,000円となっています。また、20代後半から30代前半の給与は27万3,000円~30万9,000円(大卒男女計)です。
一方、総務省統計局「家計調査(家計収支編)調査結果」厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、単身者の消費支出は約17万円、2人以上世帯では約30万円かかります。Aさんの月々の手取りは約25万円のため、単身者であれば、現状の給与が定年まで続いたとしても生活できそうです。しかし、パートナーや家族と暮らすことを考えると、このままの給与では難しいかもしれません。
Aさんの周りでは昇進や結婚などライフステージが変化している人も少なくないようですが、当のAさんは「出世や結婚とは無縁でいいからのんびり生きたい」と考えています。
人事考課面談でも「それなりに働き続けられれば、出世には興味がありません。出世すると責任が重くなるし、精神的に負荷がかかりそうで……できればこのまま定年まで静かに働き続けたいです」と話すAさんに、上司は頭を抱えます。
Aさんのように、プライベートの充実を重視した働き方を選ぶ若者は一定数存在します。しかし当然、出世しないとなれば給与収入も上がることはありません。
結婚や子育てを視野に入れると、Aさんのような働き方ではパートナーと共働きをするなど、よりいっそうの工夫や相手の理解が必要となりそうです。
さらに、老後についても懸念点があります。給与所得が低いままでは65歳以降にもらえる年金も増えません。したがって、このままの働き方を続けるのであれば、年金以外の収入源を確保したり、現役時代のうちからまとまった老後資金を準備したりと、相応の自助努力が必要でしょう。
■「静かな退職」は“スタンダード”になりえるか
Aさんのような働き方を選ぶ人が増えた場合、企業側にとっても大きな悩みの種となります。
同じ職場にAさんのような働き方の社員が増えた場合、企業の成長を妨げたり、他の労働者の就業意欲が低下したりするなど、会社にとって負の要因になる可能性があります。
出世せず静かに退職まで働きたいと希望するAさんのような人は、将来の生活像を含めて、いま一度、将来設計を考える必要があると筆者は考えます。
企業側との意思疎通ができていないと、今後、雇用の安定を望む就労に影響が出る可能性があるかもしれません。
著者:三藤 桂子 社会保険労務士法人エニシアFP・代表
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
注目の
コラム記事
-

みがく / メキメキ
2026/01/30
個人情報とは?身近な名刺データの取扱いの注意点
現代社会において、情報の価値はますます高まっています。その中でも「個人情報」は、私たちの生活やビジネ...
-

楽しむ / ワクワク
2026/01/23
ポルシェ911のリセール価値を高める装備とは?高額査定のポイント
このコラムではお車にご興味があるビジネスパーソンの皆さまへ、車の売る際の”リセールバリュー”にスポッ...
-

みがく / メキメキ
2026/01/16
透明性の高い不動産投資『REIT』とは?始め方とメリット・デメリット
※画像はイメージです/PIXTA 日本の不動産価格は高止まりの状況です。一等地の価格上昇はとどまるこ...
[ 記事カテゴリ ]
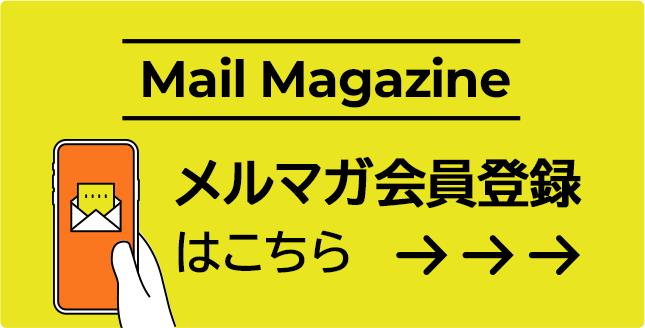
 〈新NISA〉スタートから1年半でどうなった? いまから始めても大丈夫?【元証券マンのFPが解説】
一覧へ
次の記事
〈新NISA〉スタートから1年半でどうなった? いまから始めても大丈夫?【元証券マンのFPが解説】
一覧へ
次の記事
 2027年から変わる企業会計の常識 【新リース会計基準の全貌と対応を税理士が解説】
2027年から変わる企業会計の常識 【新リース会計基準の全貌と対応を税理士が解説】