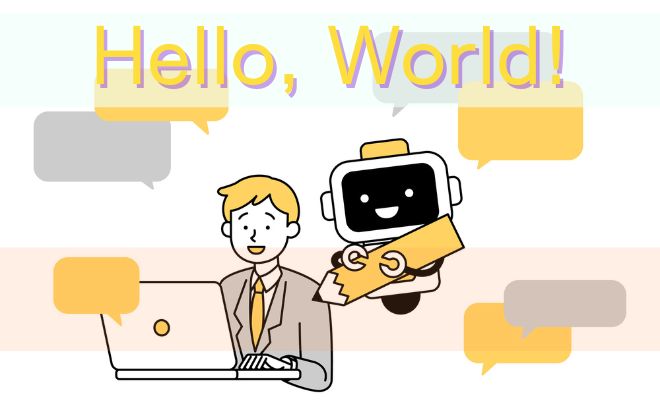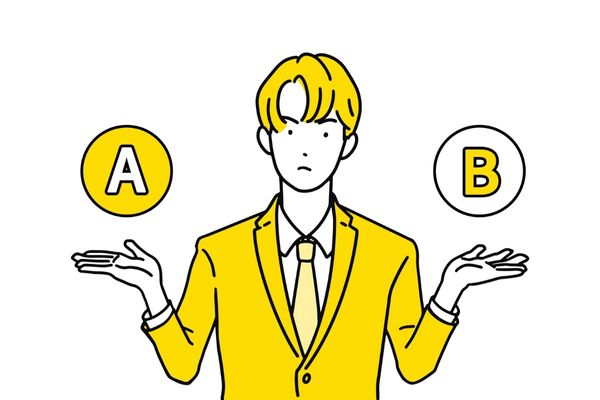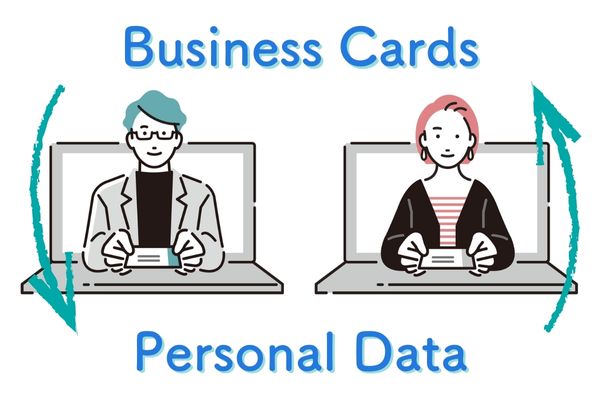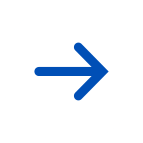コラム
2025/11/07
設備投資の検討時に『少額資産特例』はどう活用できる?
公開日:2025年11月07日 更新日:2026年01月07日

2025年度(2026年3月末)までが期限となっているこの特例、あてはまるならぜひ利用をしたい制度です。通常であれば、固定資産はその法定耐用年数に応じて減価償却を実施しますが、少額資産については即時あるいは短期間で償却できる例外が認められており、取得年度の税負担を軽減できる可能性があります。ただし、この制度は対象となる資産の金額や企業規模によって条件が異なるため、この記事で整理していきましょう。
※2025年10月時点での情報をもととした記事となります
※中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下
固定資産の減価償却の基本的な考え方
まずは基本的な考え方を確認しましょう。
例えば100万円のPOSレジを購入した場合、法定耐用年数に基づき5年間にわたって減価償却を行います。定額法の場合、1年あたりの減価償却費は取得価額(100万円)を法定耐用年数(5年)で割った20万円となります。なお、事業年度の途中で購入した場合は、20万円を12で割り、使用した月数を掛けて算出します。
※減価償却費は定額法・定率法によって算出方法が異なります。どちらの基準を採用しているかは顧問税理士にお問い合わせください。
※法定耐用年数を調べたい場合は、国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(PDF)をご覧ください。
【一括償却資産制度】20万円未満の資産取得時
取得した資産が10万円以上20万円未満の場合、「一括償却資産の特例」により3年で一括償却をすることが可能です(1年で3分の1ずつ均等償却)。資産の法定耐用年数の多くは3年超ですので、一括償却資産として会計処理することで通常の減価償却を行うより、短期間で取得価額の全額を経費計上することができます。また、事業年度の途中で購入しても3分の1ずつ償却するため、計算も簡単です。加えて償却資産税の課税対象にもなりません。
なお、こちらは後述の「少額減価償却の特例」と異なり、適用期限はなく恒久的な措置となります。
【少額減価償却資産の特例】30万円未満の資産取得時
取得した資産が30万円未満の場合、「少額減価償却資産の特例」により取得年度に全額償却できます。ただし、こちらは青色申告書を提出する中小企業等や個人事業主が対象となっていますので、対象者の詳細は国税庁のウェブサイト(外部サイト)よりご確認ください。
また、特例制度のご利用にあたっては上限と期限に注意が必要です。上限は1事業年度あたり300万円まで、期限は2026年(令和8年)3月31日までとなっています。
具体的には以下の様になります。
償却前の所得が200万円のときに、25万円の資産(法定耐用年数5年)を購入した場合。
通常の場合 償却前所得200万円-(25万円÷5)=課税所得195万円
特例の場合 償却前所得200万円-25万円=課税所得175万円
特例を利用することで課税所得に20万円の差が出ます。
| 項目 | 中小企業等の少額 減価償却資産の特例 |
一括償却資産制度 | 通常の減価償却資産制度 |
|---|---|---|---|
| 対象事業者 | 中小企業者等 | すべての事業者 | すべての事業者 |
| 対象資産 | 30万円未満の 減価償却資産 |
20万円未満の 減価償却資産 |
すべて |
| 償却方法 | 即時償却 (全額損金算入) |
3年間で均等償却 (3分の1の年償却) |
通常の減価償却 (定率法又は定額法) |
| 固定資産税 | かかる (10万円未満を除く) |
かからない | かかる |
制度が重複する場合はどちらを利用できる?
例えば15万円の資産を購入した場合、一括償却資産の特例、少額減価償却資産の特例のどちらも利用できますし、通常の減価償却を行っても問題ありません。
また、25万円の資産を購入した場合は少額減価償却資産の特例のみ利用できますが、利用せずに通常の減価償却を行っても問題ありません。
お客さまに合う制度については相談を!
費用の計上により利益が減少することになるため、場合によってはデメリットにもなり得ます。現在のお客さまの事情に最もふさわしい方法を選びましょう。判断に悩まれたら、顧問税理士や管轄税務署にご相談ください。
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
注目の
コラム記事
-

みがく / メキメキ
2026/02/13
【AIがしてくれること】 日常業務でのAI活用方法と注意点!
近年、働き方改革や人手不足、顧客ニーズの多様化を背景に、AIの導入が急速に進んでいます。営業現場でも...
-

みがく / メキメキ
2026/02/06
2種類のローン契約 「立替払契約」と「割賦販売契約」のちがい
シャープファイナンスのローン契約には「立替払契約」と「割賦販売契約」の2種類あります。どちらもお取引...
-

みがく / メキメキ
2026/01/30
個人情報とは?身近な名刺データの取扱いの注意点
現代社会において、情報の価値はますます高まっています。その中でも「個人情報」は、私たちの生活やビジネ...
[ 記事カテゴリ ]
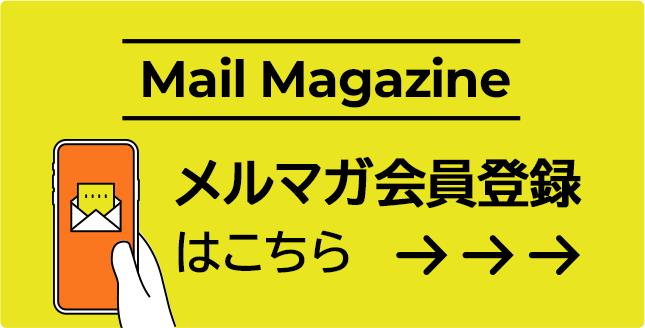
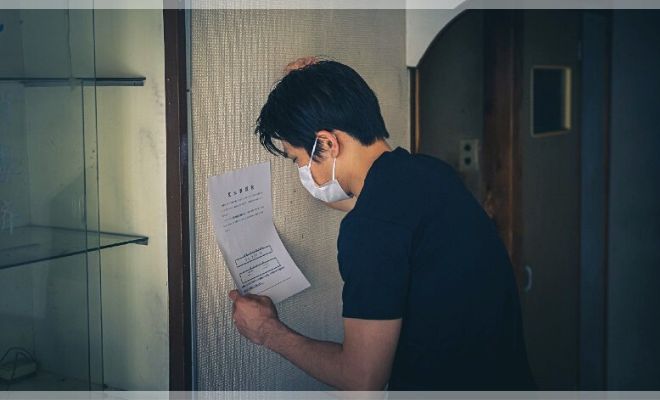 こんなはずでは…年収650万円の30代サラリーマン大家が苦汁を飲まされた「地方・高利回り物件」の落とし穴【FPの助言】
一覧へ
次の記事
こんなはずでは…年収650万円の30代サラリーマン大家が苦汁を飲まされた「地方・高利回り物件」の落とし穴【FPの助言】
一覧へ
次の記事
 上司と乗るエスカレーター「立ち位置」は前?後ろ?「昭和・平成のビジネスマナー」が身を助ける!【元大手金融出身経営者に取材】
上司と乗るエスカレーター「立ち位置」は前?後ろ?「昭和・平成のビジネスマナー」が身を助ける!【元大手金融出身経営者に取材】