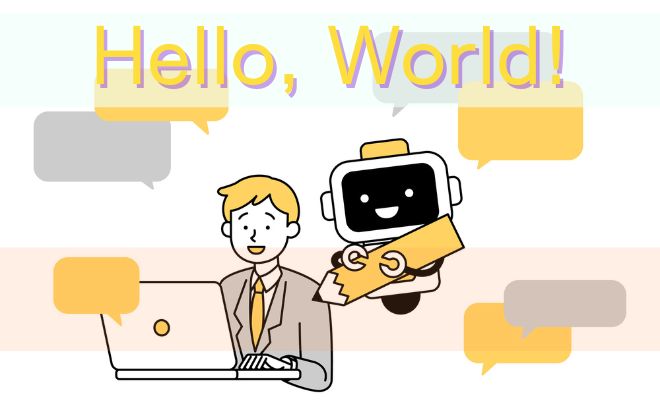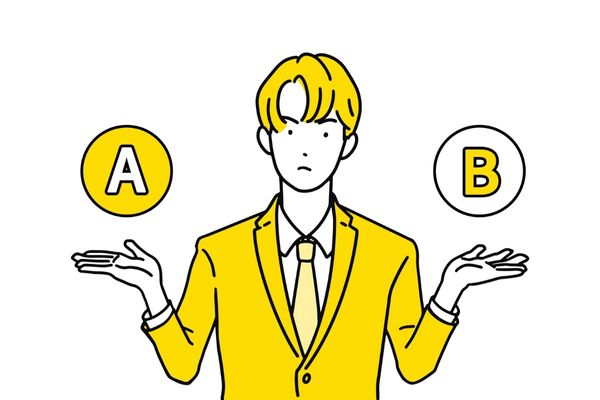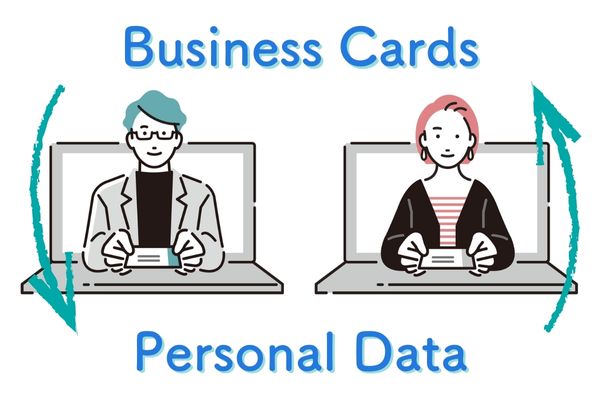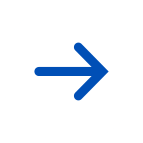コラム
2025/09/05
事業承継、待ったなし!?…大事な会社を「長生き」させる具体的な方法【専門家が解説】
公開日:2025年09月05日 更新日:2025年09月05日

※画像はイメージです/PIXTA
中小企業庁「中小企業白書(2024年版)」によると、廃業理由として「後継者不在」をあげる企業はおよそ3割(28.4%)とされています。世の中に必要とされながらも廃業を選ばざるを得ない……そんな状況を改善するための策のひとつが「M&A」です。
本稿では、株式会社船井総合研究所 あがたFASの田畑伸朗氏が「M&A」の具体的な流れと注意点を解説します。
■社長の平均年齢は過去最高…会社存続のためにできること
近年、M&A(Mergers and Acquisitions:合併と買収)市場は活況を呈しており、多くの企業が事業の拡大や再編、そして事業承継の手段としてM&Aを選択しています。
中小企業庁によれば、日本の中小企業における社長の平均年齢は2024時点で60.7歳と過去最高です。また団塊の世代が75歳以上を迎える「2025年問題」の到来も踏まえれば、事業承継を主目的としたM&Aはますます増加することでしょう。しかしながら、M&Aを選択したからといって、それが必ずしも成功するものではありません。成功のためには具体的な流れ、事前の準備、注意点をしっかりと把握しておく必要があります。そこでM&Aの具体的な流れや注意点について「売り手(譲渡側)目線」でみていきましょう。
■準備からクロージングまで…「M&A」の具体的な流れ
M&Aは一般的に以下の流れで進んでいきます。
1.準備段階
・自社の強みや弱みの分析
・企業価値の把握
・M&Aアドバイザーの選定
・秘密保持契約の締結
2.買い手探索
・買い手候補リストの作成
・買い手候補への打診
・買い手から「買収意向表明書」を受け取る
3.交渉・買収監査
・買い手と条件交渉を行う
・買い手から詳細な調査(デューデリジェンス:買収監査)を受ける
4.最終契約・クロージング
・最終契約書の締結
・株式譲渡や事業譲渡の手続きを行う
売り手の立場としては、各ステップにおいて主体的に行動し、不利な条件でM&Aを進めないように注意する必要があります。
なお、「1.準備段階」のなかにある「M&Aアドバイザーの選定」は必須ではありません。しかし、有利に条件交渉を行うには一定の経験値が必要であることや、買い手の探索や打診、交渉には相当な手間と労力を要することを鑑みると、利用したほうが安全でしょう。
また、自社の特性分析や企業価値の把握は第三者目線でないと正確には把握できないため、そういう意味でもM&Aアドバイザーの利用をおすすめします。
■ 成功を左右する「事前準備」
M&Aを成功させるためには、事前の準備が非常に重要です。特に企業価値を高めるための取り組みはM&Aの成否を大きく左右します。
重要な事前準備は「財務状況の改善」「経営体制の強化」「事業の磨き上げ」の3つです。
1.財務状況の改善
・収益性の向上(公私の分別、事業別・拠点別収益状況の把握など)
・資産の整理(貸付金の整理、不明瞭な投資勘定の削減など)
・負債の圧縮(有利子負債の削減など)
・会計処理の適正化(適正な減価償却の実施、退職給付引当金の計上など)
2.経営体制の強化
・組織体制の見直し(組織図の作成など)
・内部統制の強化(各種規程の整備など)
・人材育成(キャリアプランの作成など)
・経営計画の作成(単年度計画、中期経営計画の策定など)
3.事業の磨き上げ
・競争優位性の確立
・新規事業の開設
・顧客満足度の向上
・ブランド力の強化
1つひとつの項目自体は特殊なものではなく、中小企業の経営を行っていくうえで当たり前のものでしょう。しかしポイントは、これらを資料として第三者に説明できるレベルまで持っていくことです。
実際、「将来の事業計画について頭の中で構想はあるものの、説明できるような資料はなにもない」「事業ごとの状況は体感では把握しているものの、事業別収支表など目に見える形では作成していない」など、この“客観性”でつまずく譲渡企業は少なくありません。
日頃からこれらの準備を行うことで買い手企業からの評価を高め、より有利な条件でM&Aを進めることが可能となります。
■タイミングを誤ると不利…M&A「4つ」の注意点
M&Aは事業承継の有効な手段のひとつですが、いくつか注意すべき点も存在します。主な注意点は下記の4つです。
1.タイミング
年齢や健康状態を考慮し、早めの検討開始を心がけましょう。業績が悪化してからでは、買い手が見つかりにくくなります。
2.情報開示
従業員や取引先への情報開示は慎重に行うようにしましょう。これは、情報漏洩による事業への影響を最小限に抑えるためです。
3.交渉
M&Aでは感情的にならず、あくまでも冷静に交渉する必要があります。そのためには、譲れない条件を明確にしておき、優先順位を決めておくとよいでしょう。
4.従業員の処遇
従業員の雇用維持や労働条件についても、買い手としっかりと協議することが大切です。また、従業員の不安を取り除くためにも、日頃からコミュニケーションを密にとっておくことをおすすめします。
特に強調したいのは、適切なタイミングで検討を開始することです。一般的に、M&Aが成立するには早くて1年程度、通常であれば2~3年程度を必要とします。また場合によっては、3年で成約には至らないケースも珍しくはありません。
したがって、自身の年齢や健康状態、業界動向などを踏まえて、検討開始時期を逆算する必要があります。追い込まれた状態で検討を開始するようでは、当然ながら有利に交渉を進めることはできません。
■綿密な「戦略」が成功のカギ…慎重に作戦を立てて
M&Aの成功には「事前準備」と「情報収集」が欠かせません。市場の現状を把握し、具体的な流れを理解し、日頃から企業価値を高めるための努力を怠らないことが重要です。また、事業承継においてはタイミングや情報開示、交渉、従業員の処遇など、注意すべき点が多岐にわたります。専門家のアドバイスを受けながら、期間に余裕をもって慎重に検討を進めましょう。
〈著者情報〉
田畑 伸朗
株式会社船井総合研究所あがたFAS チーフコンサルタント
(編集:幻冬舎ゴールドオンライン)
提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス
注目の
コラム記事
-

みがく / メキメキ
2026/02/13
【AIがしてくれること】 日常業務でのAI活用方法と注意点!
近年、働き方改革や人手不足、顧客ニーズの多様化を背景に、AIの導入が急速に進んでいます。営業現場でも...
-

みがく / メキメキ
2026/02/06
2種類のローン契約 「立替払契約」と「割賦販売契約」のちがい
シャープファイナンスのローン契約には「立替払契約」と「割賦販売契約」の2種類あります。どちらもお取引...
-

みがく / メキメキ
2026/01/30
個人情報とは?身近な名刺データの取扱いの注意点
現代社会において、情報の価値はますます高まっています。その中でも「個人情報」は、私たちの生活やビジネ...
[ 記事カテゴリ ]
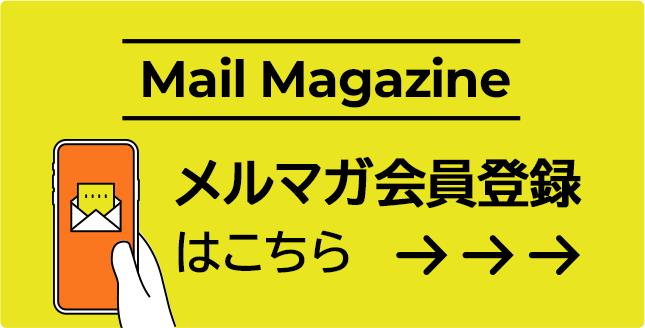
 金利は上がり続ける?…マイホームを買う前に知っておきたい「住宅ローン」の賢い選び方【お金のプロが解説】
一覧へ
次の記事
金利は上がり続ける?…マイホームを買う前に知っておきたい「住宅ローン」の賢い選び方【お金のプロが解説】
一覧へ
次の記事
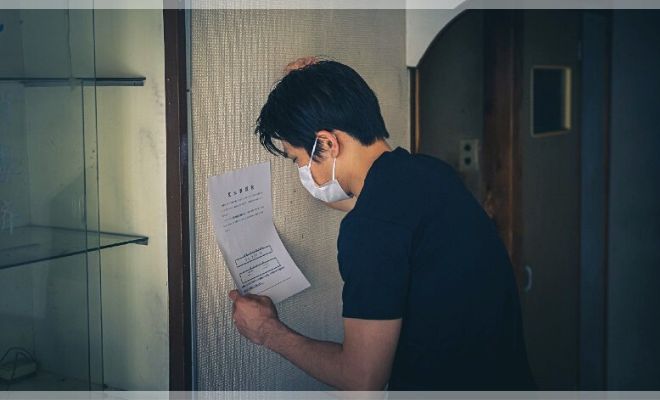 こんなはずでは…年収650万円の30代サラリーマン大家が苦汁を飲まされた「地方・高利回り物件」の落とし穴【FPの助言】
こんなはずでは…年収650万円の30代サラリーマン大家が苦汁を飲まされた「地方・高利回り物件」の落とし穴【FPの助言】